限界からの一歩
公園からは子ども達の弾む声が、校舎からは吹奏楽部の演奏のメロディーが、校庭からはボールを打ち、ボールを蹴る音が聴こえてくる。
耳で夏休みを感じながら、仕事に行った今朝。
私の仕事も夏休みモードに入る。
生活の流れの変化に合わせて、発達に向き合うリズムも変えていく必要がある。
夏休み前、偶然にも同じ言葉を使う、私がいた。
「限界からの一歩」
本人も、親御さんも、先生も、支援者も、見ている、感じている限界のラインがある。
そこを一歩踏み出そうというのが、この意味である。
限界のラインから下がったところで足踏みをし、充分慣れ、余裕ができるまで待つという考え方がある。
これは無理なく、楽になるくらいまで成長すれば、自ずと限界のラインが上がっていくだろう、というものである。
一方で、全力で限界のラインを超えることで、限界そのものを上げていこうという考え方もある。
私は趣味でマラソンをしているが、楽なペースでいくら走り続けても、楽なペースで長く走れるようになるだけで、タイムは伸びないと実感している。
本気でタイムを縮めようとしたら、自分の限界ラインを超える必要がある、そう考えている。
限界を超えた先にこそ成長があり、限界を超えた時点で、限界そのものがそこにはなかったことに気が付ける。
そもそも限界ラインとは、頭が作りだした幻想であり、言い訳が仮装したようなものである。
私が関わる子ども達を見ていると、限界ラインを超えるような経験をしていない雰囲気を感じる。
いや、むしろ、周囲の大人によって「ここに、きみの限界ラインがあるよ」「限界まで頑張ると疲れちゃうよ」と、あたかも明確な限界ラインが存在するように、またその限界ラインに近づかないように、とされてきたように思えてくる。
だから私は、この夏休み、彼らの思う、親御さんの思う限界ラインを超えてもらう経験をしてもらいたいと願いから「限界からの一歩」という言葉を使っているのだろう。
子ども達、親御さん達から漂う“限界ライン”という幻想を目にすると、ギョーカイの営業トークを連想する。
「生涯に渡る支援」は、支援からの卒業の手前に限界のラインを引く。
「支援があれば」は、支援を必要としない自立の手前に限界のラインを引き、「専門家がいれば」は、専門家ではない親御さんや本人の力だけでは限界がある、というメッセージを伝える。
「一生治りません」は、改善と治るの間に限界のラインを引くようなもの。
つまり、ギョーカイの営業トークとは、支援者の望む範囲に限界ラインを引き、その限界ラインを本人に、親御さんに見えるようにすることが目的だといえる。
支援者からの自立の手前に、当事者の可能性の、生活の、人生の限界ラインを引く。
その限界ラインを超えないように、近づかないように、それがギョーカイの支援であり、ギョーカイの支援の、能力の限界ラインとも言える。
この夏休みは、みんなに自分の限界ラインを超えてもらおうと思っている。
「もう無理かも」「もう難しいかも」「これが限界かも」
そういった思いが浮かんできたからの一歩を後押ししたいと考えている。
限界ラインを見て走るのではなく、自分の過去よりも成長した姿を見て走ってもらいたい。
そして親御さんには、ギョーカイの囁きによって、知らず知らずに植え付けられた限界ラインを壊してもらいたい。
遊び疲れた子どもが食事中ウトウトするように、脳内の、他人の作った限界から飛びだして、夜には心地良い眠りに誘えるような発達援助を目指していく。
耳で夏休みを感じながら、仕事に行った今朝。
私の仕事も夏休みモードに入る。
生活の流れの変化に合わせて、発達に向き合うリズムも変えていく必要がある。
夏休み前、偶然にも同じ言葉を使う、私がいた。
「限界からの一歩」
本人も、親御さんも、先生も、支援者も、見ている、感じている限界のラインがある。
そこを一歩踏み出そうというのが、この意味である。
限界のラインから下がったところで足踏みをし、充分慣れ、余裕ができるまで待つという考え方がある。
これは無理なく、楽になるくらいまで成長すれば、自ずと限界のラインが上がっていくだろう、というものである。
一方で、全力で限界のラインを超えることで、限界そのものを上げていこうという考え方もある。
私は趣味でマラソンをしているが、楽なペースでいくら走り続けても、楽なペースで長く走れるようになるだけで、タイムは伸びないと実感している。
本気でタイムを縮めようとしたら、自分の限界ラインを超える必要がある、そう考えている。
限界を超えた先にこそ成長があり、限界を超えた時点で、限界そのものがそこにはなかったことに気が付ける。
そもそも限界ラインとは、頭が作りだした幻想であり、言い訳が仮装したようなものである。
私が関わる子ども達を見ていると、限界ラインを超えるような経験をしていない雰囲気を感じる。
いや、むしろ、周囲の大人によって「ここに、きみの限界ラインがあるよ」「限界まで頑張ると疲れちゃうよ」と、あたかも明確な限界ラインが存在するように、またその限界ラインに近づかないように、とされてきたように思えてくる。
だから私は、この夏休み、彼らの思う、親御さんの思う限界ラインを超えてもらう経験をしてもらいたいと願いから「限界からの一歩」という言葉を使っているのだろう。
子ども達、親御さん達から漂う“限界ライン”という幻想を目にすると、ギョーカイの営業トークを連想する。
「生涯に渡る支援」は、支援からの卒業の手前に限界のラインを引く。
「支援があれば」は、支援を必要としない自立の手前に限界のラインを引き、「専門家がいれば」は、専門家ではない親御さんや本人の力だけでは限界がある、というメッセージを伝える。
「一生治りません」は、改善と治るの間に限界のラインを引くようなもの。
つまり、ギョーカイの営業トークとは、支援者の望む範囲に限界ラインを引き、その限界ラインを本人に、親御さんに見えるようにすることが目的だといえる。
支援者からの自立の手前に、当事者の可能性の、生活の、人生の限界ラインを引く。
その限界ラインを超えないように、近づかないように、それがギョーカイの支援であり、ギョーカイの支援の、能力の限界ラインとも言える。
この夏休みは、みんなに自分の限界ラインを超えてもらおうと思っている。
「もう無理かも」「もう難しいかも」「これが限界かも」
そういった思いが浮かんできたからの一歩を後押ししたいと考えている。
限界ラインを見て走るのではなく、自分の過去よりも成長した姿を見て走ってもらいたい。
そして親御さんには、ギョーカイの囁きによって、知らず知らずに植え付けられた限界ラインを壊してもらいたい。
遊び疲れた子どもが食事中ウトウトするように、脳内の、他人の作った限界から飛びだして、夜には心地良い眠りに誘えるような発達援助を目指していく。

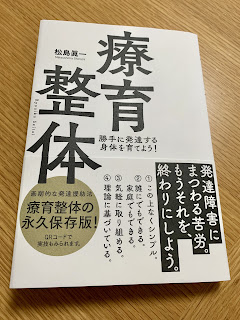
コメント
コメントを投稿